2008年5月10日5:18 PM
 GW最終日。気合いを入れて朝4時起き。琵琶湖へと向かう。いつもは、琵琶湖大橋辺りでくすぶっていたので、その日は前日にWEBで下調べをして石田川下流域にスポットを絞り込んだ。現場に到着したのは、朝6時ぐらいだっただろうか?眩しい朝日の中、石田川の上を鳥が気持ちよさそうに飛行していた。かなり早く到着したつもりだったが、ウェーダーを装着したアングラー達が既にバスを狙っていた。流石名だたるスポットだけ有り魚影は濃い。しかし、同時に魚たちのスレ具合も半端ではない。見えバス達は彼らが見えるその方向へ顔を向けただけで、水底の見えない場所へ潜ってしまう。時間が過ぎて、石田川北側にある漁港は、いつの間にか釣り堀状態となる。それだけ人がいたにもかかわらず、まともなバスをゲットしたのはいかにも見た目にベテランという感じのアングラー1名のみ。
GW最終日。気合いを入れて朝4時起き。琵琶湖へと向かう。いつもは、琵琶湖大橋辺りでくすぶっていたので、その日は前日にWEBで下調べをして石田川下流域にスポットを絞り込んだ。現場に到着したのは、朝6時ぐらいだっただろうか?眩しい朝日の中、石田川の上を鳥が気持ちよさそうに飛行していた。かなり早く到着したつもりだったが、ウェーダーを装着したアングラー達が既にバスを狙っていた。流石名だたるスポットだけ有り魚影は濃い。しかし、同時に魚たちのスレ具合も半端ではない。見えバス達は彼らが見えるその方向へ顔を向けただけで、水底の見えない場所へ潜ってしまう。時間が過ぎて、石田川北側にある漁港は、いつの間にか釣り堀状態となる。それだけ人がいたにもかかわらず、まともなバスをゲットしたのはいかにも見た目にベテランという感じのアングラー1名のみ。
釣果はともかくこの石田川漁港のすぐ北側には幅が1メートルぐらいの川があり、その川の透明度には感動しました。その川から琵琶湖へ無数の鮎たちが下り、気持ちよさそうに群れをなして縦横無尽泳いでいました。

この様な、美しい環境の中で微睡みたいなと、後ろ髪を引かれながら釣果を求めて場所を移動。
あまりのバスのスレ具合に辟易としたため水の透明度の低い近くの野池へ。思惑通り20cm程の小バスを何匹かゲット。恥ずかしながら、本日の自分の釣果はこの小バスのみとなる。一緒に同行した次男は同じサイズのバスを5匹ほどゲットする。
サイズには満足できなかったが、そこそこの数を釣ったのでバス釣りはココで一段落。

次に向かったのはびわ湖バレイでした。そんなに期待はしていなかったのですが、30万本植えたと言う水仙の花達は想像を絶する美しさでした。この日は、熱いぐらいの陽気でしたが標高1100mなので心地好いことこの上ありませんでした。蓬莱山迄の道のりはかなりの勾配でしたが、難なく登ることが出来ました。
そして、ここでも結局ホッコリする間なくさらなる釣果を求めて移動。







 意識的になのか無意識なのか定かではないが、京都でのイベントに出かける機会が続く。
意識的になのか無意識なのか定かではないが、京都でのイベントに出かける機会が続く。 これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「
これからの活躍が期待されていたのにもかかわらず1937年に28歳の若さで心臓麻痺のためその生涯を閉じたという音楽家、大阪府吹田市出身その後芦屋市にも居住した貴志康一氏。彼が作曲した作品は1949年日本人として初めて湯川秀樹氏がノーベル賞を受賞したその後の晩餐会で楽曲が流れるという栄誉を持つ。その様な、間もなく生誕100周年を迎える同氏の音楽が京都の「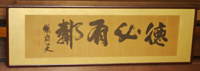 20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。
20年以上のお付き合いであるNさんに招待されて行ったこのコンサートは、私にとってとても不思議な因縁を感じるコンサートでもありました。